システム生物学って何だったんですか?(後編)
はじめに
「システム生物学って何だったんですか?(前編)」に引き続き、日本におけるシステム生物学(的)研究のその後について、書いていきたいと思います。
まだ読んでいない人は、前編はこちら
後編は前編で触れていなかった金子邦彦さんや生物物理からの流れからはじめ、2005年以降の定着期にの話が中心になります。
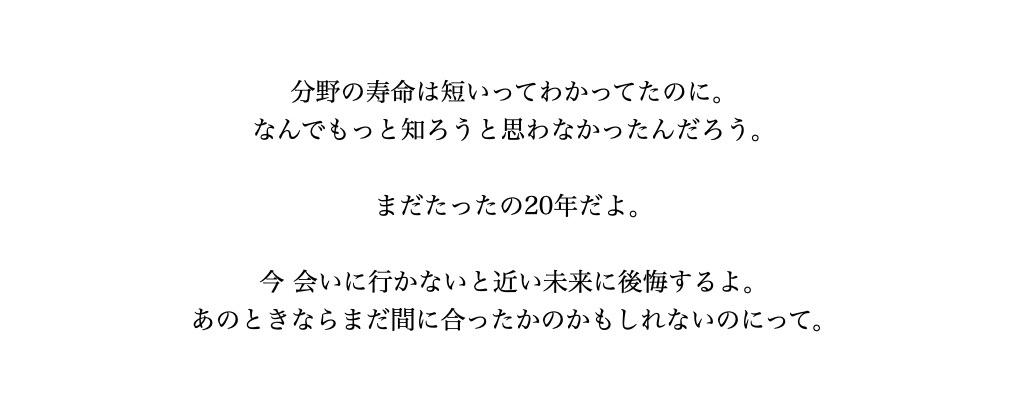
文献[1]より引用・改変。
複雑系からシステム生物学へ
システム生物学黎明期においては、北野さん、黒田さん、上田さん、望月さんなど比較的少数の志のある人々が”システム生物学的”な研究に取り組んできたわけですが、研究分野が広がるという意味では、研究テーマのフィロソフィーを受け継いで研究を実践する人材をどれだけ輩出できるかというのが重要になります。
人材を育成し、分野を広げるという観点で2005年ごろから現在に至るまで大きな影響があるのが、東大駒場の総合文化研究科と金子邦彦さんです。
駒場COEと人材育成
総合文化では金子さんを代表として1999年からCOE(Center Of Excellence Program)「複雑系としての生命システムの解析」(代表:金子邦彦)を実施し、この活動は2002年度からの21世紀COE「融合科学創成ステーション」(代表:浅島誠)と引き継がれ、2005年からは複雑系生命システム研究センターが設立されています。
「複雑系としての生命システムの解析」という名前が示すように、このプログラムは複雑系の観点で生命システムの理解を目指すという日本の複雑系研究の延長に位置するものであり、かつ総合文化研究科の物理から生物まで広い分野を扱う理論系・実験系グループがこの教育プログラムに従事しました。
このプログラムは北野さんの「ERATO 北野共生システムプロジェクト」 (1998-2003)とほぼ同時に実施されています。
このCOEでの研究から当時のシステム生物学に大きなインパクトがあるような成果があったかというと、正直あまり思いつかないのですが、その後の物理的な視点での生命科学や定量的な生命科学研究につながる試み、特に実験系のそれが、教育と合わせてなされています。後で述べますが、このプログラムの期間に駒場で学位を取った学生が、その後この分野で活躍をしています。その観点から、このCOEプログラムは日本におけるシステム生物学(的)研究の人的な基礎を築いたと言っても過言ではないと思います。
複雑系との決別としてのシステム生物学
しかしこのCOEが、「複雑系としての生命システムの解析」と掲げるように複雑系とシステム的な理解(システム生物学)をシームレスに繋いだかのか?というと必ずしもそうではありません。
むしろ当時、システム生物学は複雑系的な研究と決別した新しい研究先としての位置づけがあり、特に理論系は複雑系からの鞍替えとしてシステム生物学へ人材が流れたという側面があります。
「複雑系はなぜ廃れてしまったか?(私的考察)」で考察しているように、1990年代、複雑系は一世を風靡する人気分野でした。しかし風呂敷を広げすぎたせいで、この分野に有象無象が群がりバズワード(近藤さん的はジンクピリチオンワード)として消費されました。また、生命科学にも関わる重要な問いを多く提起しましたが、複雑系としてその問いを解決し、体系化することは十分にできませんでした。また理論的・哲学的議論が先行して実験と完全に乖離し、言っていることとやれていることに大きなギャップがあったのも2000年になると強く認識されるようになっていました。
これに対して2000年ごろから現れたシステム生物学では、北野さんの「生命をシステムとして理解する」というスローガンはさておき、海外では現象の定量的な計測と解析など、過去の複雑系に欠けていた実験研究が現れていました。例えば、複雑系が仮定していた生命の高次元状態をマイクロアレイのような技術で計測したり、当時最先端だったイメージング技術により生体の遺伝子発現やダイナミクスを経時的に測るような試み、そして遺伝工学を用いて実際に特定の性質を持つことが期待される系を構成して考える、という研究です。
システム生物学が始まった当時は、こういう先駆的な試みというのが色々な方面で行われているような状況でした。そしてその対象は主に、バクテリアや酵母などの化学走性や概日リズムなどの基本的な現象です。
これらの現象は、すでに主たる対象が哺乳類などの高等生物に移っていた分子生物学では、当時から ”終わった対象” と思われており、また複雑系的にも振動などは、複雑系以前に自己組織化とか散逸構造とかで扱われていた ”単純すぎるやはりおわった現象”、という認識があったと思います。しかし分子同定の意味では終わった現象でも、特定の分子の組み合わせで非自明な生体のダイナミクスがなぜ現れるのか、振動や記憶などの理論的には単純な現象でも実際の生き物で理論が思うようなことが本当におきているのか、などはきっちりと示されておらず、こうした研究をすくい上げる場として、システム生物学の領域は国際的に機能したと思われます。
このような背景もあり、理論面では金子研で当時複雑系を研究して学位を取得したメンバーである、現在理研の柴田達夫さん(1998年度卒)、広島大学の藤本 仰一さん(2000年度卒)、奈良医大の高木 拓明さん(2001年度卒)、立命館大学の冨樫 祐一さん(2003年度卒)、東大総合文化の石原 秀至さん(2004年度卒)などが学位取得後に複雑系からシステム生物的研究、特に実験と理論の融合研究に転向していきました。
唯一の例外は現在東大物理の古澤力さん(1999年度卒)で、卒業後、基礎特別研究員(2001-2003)として理研CDBの西川伸一研究室でES細胞系の実験系に従事し、金子さんの共同研究者として一貫して複雑系生物学を実験と理論の両面で探求・実践しています。
また、COEを卒業した実験研究者の方々も海外の関連研究室などに留学をしてゆくことになります。
(余談) 名前を言えないあの分野
2005年ごろのこの時期は「複雑系を研究している」ということを宣言することが一般に憚れるような雰囲気があり、自分も含め複雑系から距離をおく傾向がありました。それは複雑系ブームが人々、特にそれに関わっていない周辺の人々に残した悪い印象やイメージもありますし、学生として複雑系に関わった若手の間でも、複雑系ができていないことが明確になるにしたがいアンチ複雑系的な立ち位置が芽生えていたのもあるかと思います。とはいえ20年も経つと、そんな雰囲気も当時の熱気とともに、当事者だった人々を除いてすっかり忘れ去られ、今やおとぎ話の様になっています。

文献[2]より引用・改変。
システム生物学からの離脱
前編でも記載したように、初期のシステム生物学は分野もアプローチもなんでもありのお祭り状態・手探り状態でしたが、その試みの中で次第とうまくゆく研究のアプローチやコアとなる技術が確立し、システム生物学から分離・離脱してゆくという傾向が2005年前後から顕在化していきます。
その代表がオミクス系で、2005年の次世代シーケンサーの登場とともに、ゲノム関連からシステム生物学に流れてきた多くの研究者は離脱してゆくことになります。日本ではNGS現場の会(2011年第一回、現在は閉会)なども結成され、分子生物学研究との連続性の高さから強力な分野へと発展していきます。
もう一つはイメージング技術を用いた定量的・経時的な計測に理論やデータ解析を組み合わせる流れ、これは生物物理研究などと合流して次第に定量生物学へとつながっていきます。
そして最後は、生命を作って理解する、役に立つ生体システムを創るという、構成生物学、合成生物学、分子ロボティクスなどの流れです。

システム生物学から定量生物学へ
システム生物学登場時の2000年ごろはまだ研究の最前線で(多分)よそ見をする余地のなかった1分子計測を中心とした生物物理分野ですが、2005年頃には1分子で確立したイメージング技術を基盤として、次の研究の方向性として細胞や細胞集団の現象、つまりシステム生物で扱ってきたものに取り組む先駆的な試みが現れ始めてきます。阪大生命機能の上田 昌宏さんなどが細胞性粘菌を使ったイメージング研究を開始しています。
日本においては、金子研で学位を取った高木さんが1分子計測の柳田研に研究員で着任し、その後、日本の生物物理実験コミュニティと金子研から輩出される理論研究者との橋渡しを行っています。
また、形や形態をみるという必然性から発生生物学もイメージング技術を積極的に導入しており、イメージングで得られた情報を活用する観点で、定量的な研究に関わるようになっていきます。徳島大学の堀川 一樹さん、遺伝研の木村 暁さん、東大生物情報の杉村 薫さんなどがいます。
そして他にも細胞生物学や理論生物学などでも、イメージングデータを接点とした研究への試みが個別に立ち上がってきます。
しかし実験側ではイメージング計測はできてもそれをどう解析し、解釈するべきかの方法論が全くありません。またシステム生物学へ転向してきた理論研究者にしても、どうすれば理論モデルを実験に意味のある形で繋げられるかのノウハウはありませんでした。実はそれらをつなぐには、画像解析や時系列解析、統計解析などの情報技術が必要になるわけですが、もちろんバイオデータへの情報学もまだ成立していませんので、体系どころか教科書もありません。個々の研究者が、他分野の方法を独学して真似るという状況でした。
このような背景のもと、発生・細胞・理論・生物物理・バイオインフォ・生体工学などの諸分野で、主にイメージングベースにした定量的な研究に独自に取り組む若手研究者が集まり、お互いのノウハウを共有し研究を進める場として2008年にスタートしたのが「定量生物学の会」 です。海外でもほぼ同時期の2007年にアメリカでq-bio conference とq-bioサマースクールが開始しています。
定量生物学の会は、背景とする学会を持たずそれ故にどの分野からも独立した形で、当時の若手(研究員から若手PI)により形成されたコミュニティーであり、定量研究をボトムアップに定着させることに寄与したと考えられます。
合成生物学と細胞を創る会
定量生物学の会の立ち上げは、先行する「細胞を創る会」 の設立を参考にしています。当時、上田さん、四方さんが声かけになって、人工生命、 RNA、分子化学、無細胞系、工学(MEMS)、 生命哲学などの幅広い分野の研究者を集めて結成されたこの会は、現在でも日本の人工生命研究を支えるコミュニティーになっており、システム生物学と接点のある3つ目の流れになっています。
ただ、遺伝的アルゴリズムや分子計算、生体ロボティクスなどの流れも組む日本の分子ロボティクスとも活動メンバーが重なる部分もあるので、主たる影響はシステム生物学では無い気もします。
(余談) ルネッサンスとしてのシステム生物学・定量生物学
生命科学の歴史的には、定量的な計測をもとにする研究は分子生物学以前に盛んだった細胞などを対象とした生理学や生化学の研究のリバイバルと見ることができます。岩崎秀雄さん(早稲田大学)は、生命科学におけるルネサンスと表現していました。これら昔の定量研究を見ると、定量技術で得られたデータに高度な理論モデルを組み合わせた研究が多く見られます。しかし当時の計測技術的限界から、仮説に基づく複雑な理論モデルの予想を限定的な定量計測で検証する、という形になっていき、多分「本当なのか?」という疑念がコミュニティーに存在したと想像されます。分子生物学はそんな背景の中、分子という現象の根幹にある物理的実態を同定する、というシンプルかつ明快なアプローチとそれを可能にする遺伝工学技術の発展により、70年代以降分野を塗り替えていきます。「研究領域の行き詰まりと限界」→「新たな研究プログラムの出現」の構造は、研究の歴史の必然のようにも思えます。
(余談) 日本は思想でつながるのは苦手?
定量生物学の会の立ち上げの際、名前をどうするかは議論になりました。2008年頃には複雑系と同じく、システム生物学もある意味レッテルの貼られたどちらかというとネガティブな言葉として日本では見られるようになっていました。それは近藤さんによる「システム生物はジンクピリチオン」キャンペーンなども関係していると思いますが(参考)、「生命をシステムとして理解する」に代表される研究スタイルへのスローガンや思想が先行した部分も、実験研究者などには受け入れられなかったのかとも思います。複雑系も同じような側面はあるでしょう。
研究の定着と人材の回帰
双方にネガティブなイメージが付いたシステム生物学ですが、実質的な研究の観点ではそこで育まれたアプローチは2010年以降じわじわと浸透していきました。ファンディングサポートが継続したことも、日本のコミュニティーに研究が根付く一助になったと思います。
北野さんのERATOのあとは、ERATO 金子複雑系生命プロジェクト (2004~2009)が開始し、さらにその後 四方動的微小反応場プロジェクト(2009~2014) が続きました。並行してJSTから、
- 生命システムの動作原理と基盤技術(2006~2012:CREST、2006-2012:さきがけ)
- 生命現象の革新モデルと展開(2007-2013:さきがけ)
- 細胞機能の構成的な理解と制御(2011-2017:さきがけ)
- 生命動態の理解と制御のための基盤技術の創出(2011~2019:CREST)
などの領域が連続して立ち上がっています。また、2011年には 理研 生命システム研究センター(QBiC)が柳田敏雄さんをセンター長として設置され、その後、生命機能科学研究センター(BDR)(2018年より)へと続いてしています。
そして教育面では、生命動態システム科学推進拠点事業 (2012-2016)に、
- 東大総合文化+生産研: 複雑生命システム動態研究教育拠点
- 広大:核内クロマチン・ライブダイナミクスの数理研究拠点形成
- 京大:時空間情報イメージング拠点
- 東大先端研+数理:転写の機構解明のための動態システム生物医学数理解析拠点
の4拠点が採択され、システム生物学や定量生物学に飛び込んだ若手やCOEで育った若手がPIとして新たにLabを立ち上げ、そして新たな次世代を育てるという循環がまわることになりました。東大では複雑生命システム動態研究教育拠点の活動は生物普遍性機構(UBI,2016~) として学内の組織として引き継がれ、広島大学でも関連研究者が集まる場となっています。
総括:25年間を振り返って
次の20年にむけて、システムバイオロジーの歴史から学べることを総括しこれからの展望を示したいと思います。
一般攻撃魔法になったシステム生物学
現在の生命科学研究においては、イメージングの画像解析をすることもそこから統計的に議論することも当たり前になってきましたし、数理モデルを使うことなどが特段に忌避されることも無くなりました。逆に理論系の分野でも、実験と共同した研究はむしろ分野の主流になっているように思います。
また理論ではありますが、これまでの知識の積み上げをまとめた畠山さん・姫岡さんの「システム生物学入門」も上梓され、ゾルトラークが一般攻撃魔法になったように、システム生物学の流れで育まれた技術や知識は一般生物学として同化しているように思います。
分野の定着に向けた貢献
この同化は、システム生物学初期からその後の定量生物学や諸分野の発展に関わった様々な人々の活動の結果ではありますが、やはり金子さんを中心とした東大駒場の継続的な教育・研究活動の貢献は計り知れないと思います。システム生物学から実質的には早々にフェードアウトした北野さんとは大きく異なる点です。文科省による重点的研究教育拠点などの制度も批判にのぼるところもありますが、駒場の活動はしっかりとしたビジョンを基にうまく活用すれば大きな波及効果があることを示す証左であると思います。
新しい分野は興すのか興るのか
システム生物学から定量生物に至る定着の流れを見ていると、2005年ごろまでにイメージングやシーケンスをはじめとした新技術のシーズの積み重ねにより、生命科学がかつての細胞の生理学や生化学が目指した定量的な記載や理解に回帰してゆくのは歴史的な必然だった様にも思えます。
しかしそういう研究の機運をいつ、どのタイミングで掴むのかは、研究者の先見性や嗅覚に依存しています。初期のシステム生物学はこの流れを確かに先んじて捉え、スローガンはともかく、研究分野として組織しました。おそらくですが5~10年くらいは研究の進展を自然発生的な場合と比べて早めたのではないかと思います。そして駒場の活動も立ち上がった分野を担う次世代をいち早く生み出していたという大きな貢献があります。
ではこうした機運にいち早く気づいた時、どう分野を立ち上げるのか?まだ技術や結果は実体化していない時に、これから来るであろう必然に向けてどう人々を巻き込むのか?は難しい問題です。どうしてもスローガンやビジョンを語る強い言葉やフィロソフィーなどが全面に出て、結果的に胡散臭い感じになるのも仕方ないのかもしれません。歴史から学べることは、本当に大きな変化がこれから来るという実感と確信があれば、多少ジンクピリチオン的になることも恐れずにビジョンを示し、そしてそれを目指して研究と教育をきっちりと実践してゆくことなのではないでしょうか。
反省会が終わって、複雑系生物学が始まる
分生シンポ「システム生物学大反省会」の締めは畠山さんの「反省会が終わって、システム生物学が始まる」ですが、個人的には「反省会が終わって、複雑系生物学が始まる」だと思っています。
25年にわたる定量解析への技術・知識・人材の醸成で、かつて複雑系が提起した問いや課題の一部は、実験で扱えるくらいにまで近づいていると思います。実際海外の研究などでは、昔の複雑系を彷彿とさせるような試みなどが現れています[3][4][5][6][7]。回帰が歴史の必然であれば、複雑系的な研究(その前にまずは自己組織化やもしかしたらカオスとかかもしれません)も現代的な形で再び復興するのでは無いでしょうか?それは、90年代の複雑系や金子さんの複雑系生物学とは、問いを共有しつつもかなり異なるものになるはずです。
複雑系を知らない世代が、現代の視点でどう複雑系に関連する問題や課題を発見・再定義してゆくのか、また複雑系を封印してきた2000年世代が今後その封印を解くことはあるのか、色々と楽しみにしています。
Discussion