https://youtu.be/Q6EDoHREs9Y
\textcolor{pink}{四国めたん: }
\textcolor{lime}{ずんだもん: }
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} ポインタ についてお話ししましたわ
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:} 配列 や 構造体 との関係や関数での使い方について学んだのだ
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} 大きなサイズの配列 と 動的メモリ配置 についてお話ししますわ
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} 動的メモリ配置 は頻繁に使われますわ
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:} 動的メモリ配置 ?
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} 動的メモリ配置 については、必要に応じてメモリを明示的に確保する方法ですわ
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} 動的メモリ配置 ですわね
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} 動的メモリ配置 は ポインタ とは切っても切れない関係ですわ
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
大きなサイズの配列は問題ですよ?
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
#include <stdio.h>
#define SIZE (3960 * 2048)
void main() {
int a[SIZE] = {0};
}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} int型 の配列を宣言して、0クリアするだけのプログラムですわ
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:} (3960 * 2048)と、結構、巨大なのだ
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} Stack overflow例外 は、 スタック と呼ばれるメモリの量が足りなくなった場合に発生しますわ
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:} スタック ?
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} 32440320 バイトを使用します。データの一部をヒープに移動することを考慮してください。」と云う警告も出ています
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:} ヒープ ?
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} ヒープ については、後ほど説明しますわ
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:} 例外 ?
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} 例外的な異常 が発生して、プログラムの実行が止まってしまった際に発生するシグナルですわ
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
外部変数は制限がありません
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} スタックオーバーフロー が発生する場合の対処法の1つは 外部変数 を使うことですわ
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:} 外部変数 ?
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} 外部変数 と云うのは関数の外で宣言された変数のことで、 グローバル変数 とも呼ばれますわね
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} 外部変数 は、宣言以降の関数で共通して使用できますわ
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} 外部変数 の値を変更すると、別の関数にも影響を与えることになりますわね
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} (3960 * 2048)サイズの配列を宣言して、初期化してみましょう
#include <stdio.h>
#define SIZE (3960 * 2048)
int a[SIZE];
void main() {
for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
a[i] = 0;
}
}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} 外部変数 は、一般的なコンピューターでは初期化をしなければ、自動的に0クリアされますわ
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} int a[SIZE] = {1, 2, 3};のようにすることもできますわ
動的にメモリを配置しましょう
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:} 外部変数 にデメリットはないのか?
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} 外部変数 にはサイズに対する制限が緩かったり、関数間のデータ共用が容易にできるなどのメリットがありますわ
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} 動的メモリ配置 により解決しますわ
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} 動的メモリ配置 では変数を スタック ではなく ヒープ と呼ばれる別のメモリ領域に配置しますわ
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:} スタック や ヒープ とはなんなのだ?
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} スタック は関数内で宣言した変数などに割り当てられるメモリ領域ですわ
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} ヒープ はmalloc関数をコールすることで、明示的に割り当てるメモリ領域ですわね
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:} スタック は自動的に割り当てられるメモリ領域で、 ヒープ は意図して割り当てるメモリ領域ということか
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:} スタック よりも ヒープ の方が大きいのか?
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} ヒープ の方が、はるかに大きいですわ
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} スタック のサイズが数k~数Mバイトですわ
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} ヒープ のサイズは数Gバイト以上を割り当て可能な場合も少なくありませんわ
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
malloc関数でメモリを確保
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:} malloc関数とは、なんなのだ?
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} 動的メモリ配置 によるメモリ割り当てを行うための関数ですわ
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} void *malloc(size_t size)となっていますわね
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:} size_t型 とは、どんな型なのだ?
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} size_t型 は、サイズを表すための型で「正の整数」ですわね
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:} int型 とは違うのか?
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} int型 と同じと考えて問題ありませんわ
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:} voidのポインタ型になっているのだが、意味がわからないのだ
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} ヒープ に割り当てたメモリのアドレスですわ
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} voidのポインタ型となっていますわ
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:} voidのポインタ型は、実際の型が定まっていない場合に使われるポインタ型ということか
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define SIZE (3960 * 2048)
void main() {
int* pa = (int*)malloc(sizeof(int) * SIZE);
if (pa != NULL) {
for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
*(pa + i) = 0;
}
}
}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} #include <stdlib.h>でヘッダーファイル"stdlib.h"を読み込んでいますわ
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:} malloc関数が宣言されているのだ
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} malloc関数で、 ヒープ にメモリ領域の割り当てを行っていますわ
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:} malloc関数の引数には定数以外も指定できるのか?
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} 配列 とは異なる 動的メモリ配置 のメリットのひとつですわね
sizeof演算子で型のサイズを取得します
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:} sizeofとあるが、なんなのだ?
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} sizeofは括弧内に指定した型や変数のサイズをバイト単位で返す演算子ですわ
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:} sizeof(int)は int型 が4バイトなので4が返るのか
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:} mallocの引数には、SIZEに int型 のサイズを掛けた値を渡すのか
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:} sizeof演算子の後に括弧"()"は必要なのか?
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
sizeof演算子
sizeofは、後に続く変数や配列、型のサイズをバイト単位で返す演算子です
変数や配列の場合には、sizeofの後にスペースを挟んで変数名や配列名を指定します
例えばsizeof 変数名やsizeof 配列名とします
変数名や配列名に括弧"()"を付けて、sizeof(変数名)やsizeof(配列名)としもOKです
型の場合には、sizeofの後に括弧"()"を付けて、その内に型名を指定します
例えばsizeof(型名)とします
ただ、型の場合には、括弧"()"を使わずにsizeof 型名とすることはできません
include <stdio.h>
void main() {
int a = 0;
int b[] = {0, 1, 2, 3, 4};
int s = sizeof a;
int t = sizeof(int);
int u = sizeof b;
printf("int型の変数のサイズは%dです\n", s);
printf("int型のサイズは%dです\n", t);
printf("int型の配列の要素数は%dです\n", (u / t));
}
上記例では、コンソールに
int型の変数のサイズは4です
int型のサイズは4です
int型の配列の要素数は5です
と表示されます
なお、sizeof 配列名だけでは、配列の要素数ではなく、バイト数が返ります
配列の要素数を得るためには、sizeof 配列名 / sizeof(配列の型)もしくはsizeof 配列名 / sizeof 配列[0]とします
ポインタにsizeof演算子
!
ポインタにsizeof演算子を使う場合には注意が必要です
以前にポインタと配列は同じように扱えるとお話ししました
ただ、ポインタに配列を代入したからと言って、ポインタにsizeof演算子を使っても、配列のサイズは得られません
ポインタはアドレスを入れるための変数ですので、sizeof演算子によって得られる値は、アドレスのサイズになります
以下のプログラムを実行すれば、違いは明確です
#include <stdio.h>
void main() {
int a[] = {0, 1, 2, 3, 4};
int* pa = a;
int s = sizeof a;
int t = sizeof pa;
printf("配列のサイズは%dです\n", s);
printf("ポインタのサイズは%dです\n", t);
}
結果は以下のようになります
ベテランのプログラマでも混同してしまうことが多いので、注意が必要です
キャスト演算子で型を変えます
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:} mallocの前に付加した(int*)は、なんなのだ?
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} mallocの前に付加した(int*)が キャスト演算子 ですわ
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:} キャスト演算子 ?
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} (型)という形で付けて、型を括弧内の型に強制的に変更する演算子ですわ
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} void*型 の戻り値を強制的に int*型 に変更していますわね
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} キャスト演算子 は強力すぎてバグの温床になりますので、多用は厳禁ですわ
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} malloc関数の戻り値に使うのは、例外的に必須となりますわね
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
NULLの戻り値
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} malloc関数で 動的メモリ配置 が失敗した場合にはNULLが返りますわ
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:} NULLかどうかの確認をしているのか
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} forループで初期化を行う前にif文で戻り値がNULLではないことを確認していますわ
free関数でメモリを解放
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} free関数を使いますわ
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:} free関数?
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} void free(void* block)という形式の関数になりますわね
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define SIZE (3960 * 2048)
void main() {
int* pa = (int*)malloc(sizeof(int) * SIZE);
if (pa != NULL) {
for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
*(pa + i) = 0;
}
}
free(pa);
pa = NULL;
}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} free関数の引数の型は void*型 ですわ
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:} voidのポインタ型ということは、実際の型が定まっていないということか?
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} malloc関数で得られた値をそのままセットするようにしますわ
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:} malloc関数で得られた値以外はダメなのか?
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} free関数の引数に渡せる値は限定されていますわ
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} free関数でメモリ領域を解放した後のポインタは必ずNULLにしておきますわ
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
NULLの引数について
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:} malloc関数が失敗してpaにNULLがセットされている場合にfree関数の引数にNULLが渡されるのではないか?
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} free関数の引数にNULLを指定した場合には、何もしないことになっていますわ
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:} NULLはfree関数の引数にセットできる値の1つということか
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
動的メモリ配置は解放まで有効
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} mallocで割り当てられたメモリ領域は、関数を抜けた後はどうなるのでしょうか?
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:} freeで解放するまでは有効なのではないか?
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} mallocで割り当てられたメモリ領域のポインタを戻り値として返してもOKなのですわ
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define SIZE (3960 * 2048)
int* get_array() {
int* p = (int*)malloc(sizeof(int) * SIZE);
return p;
}
void main() {
int* pa = get_array();
if (pa != NULL) {
for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
*(pa + i) = 0;
}
}
free(pa);
pa = NULL;
}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} get_array関数内でmallocに割り当てたメモリ領域は、メイン関数でもfreeが呼ばれるまでは有効ですわ
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} freeでの解放を忘れることが多いので充分な注意が必要ですわ
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
動的メモリ配置用の関数は他にもあります
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:} 動的メモリ配置 を行える関数はmallocだけなのか?
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} 動的メモリ配置 を行える関数としては、他にもcallocやrealloc等がありますわ
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} malloc以外は、余り使い勝手が良い関数ではありませんわ
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} mallocで済んでしまいますので、問題ありませんわ
calloc / realloc
動的メモリ配置 を行う関数はmallocの他にcallocやreallocがあります
どちらもmallocで簡単に代用できるので、できるだけmallocを使うようにして下さい
calloc
形式はvoid *calloc(size_t count, size_t size);となります
指定されたサイズのメモリ領域をヒープ領域に確保し、0でクリアします
mallocとの最大の違いは、取得したメモリ領域を0でクリアすることです
また、引数では、"size"に確保するメモリの型のサイズを、"count"には要素数を指定します
例えば、配列int a[100];と同じメモリ領域を取得する場合には、"size"にはsizeof(int)を、"cont"には100を指定します。
mallocと比べて、メモリサイズをバイト単位に変換する必要がないことと、0による初期化が必要ないメリットがあります
ただ、メモリサイズのバイト単位への変換は掛け算ひとつで済んでしまいますし、0以外の初期化を必要とする場合には2度手間になってしまいます
mallocを使って同じことができます
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
void* another_calloc(size_t count, size_t size) {
size_t num = count * size;
void* p = malloc(num);
if (p != NULL) {
memset(p, 0, num);
}
return p;
}
関数名はcallocにすると被ってしまいますのでanother_callocとしています
memsetは指定したメモリ領域を指定の値で埋める関数で、"string.h"内で宣言されています
形式はvoid *memset(void* ptr, int value, size_t num);となります
"ptr"はメモリ領域の先頭アドレス、"value"はセットする値、"num"はメモリサイズでバイト単位です
memsetは次回に詳細を説明します
realloc
形式はvoid* realloc(void* ptr, size_t size);となります
指定したメモリ領域のサイズを指定のサイズに変更します
"size"で指定したサイズのメモリ領域を確保し、"ptr"で指定したメモリ領域の値をコピーします
"ptr"で指定したメモリ領域は解放され、新たに確保されたメモリ領域が返ります
なお、"size"で指定した値が元のメモリ領域のサイズよりも小さい場合には、コピーできない部分の値は破棄されます
また、"size"で指定した値が元のメモリ領域のサイズよりも大きい場合には、値がコピーされた部分以外は不定の値がセットされます
色々と細かい部分は省いて、基本的にはmalloc関数を使って同じことができます
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
void* another_realloc(void* ptr, size_t size) {
void* p = malloc(size);
if (p != NULL) {
memmove(p, ptr, size);
free(ptr);
}
return p;
}
関数名はreallocにすると被ってしまいますのでanother_reallocとしています
memmoveは指定したメモリ領域の値を指定のメモリ領域に移動する関数で、"string.h"内で宣言されています
形式はvoid* memmove(void* destination, const void* source, size_t num);となります
"destination"は移動先のメモリ領域の先頭アドレス、"source"は移動元のメモリ領域の先頭アドレス、"num"は移動するサイズでバイト単位です
memmoveは次回に詳細を説明します
reallocは動作が処理系により違っていたり、使い方が独特でバグの温床になり易いので、多用は避けるべきです
まとめ
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:}
\footnotesize \textcolor{lime}{ずんだもん:}
\footnotesize \textcolor{pink}{四国めたん:} 大きなサイズの配列と動的メモリ配置 についての説明は終わりですわ
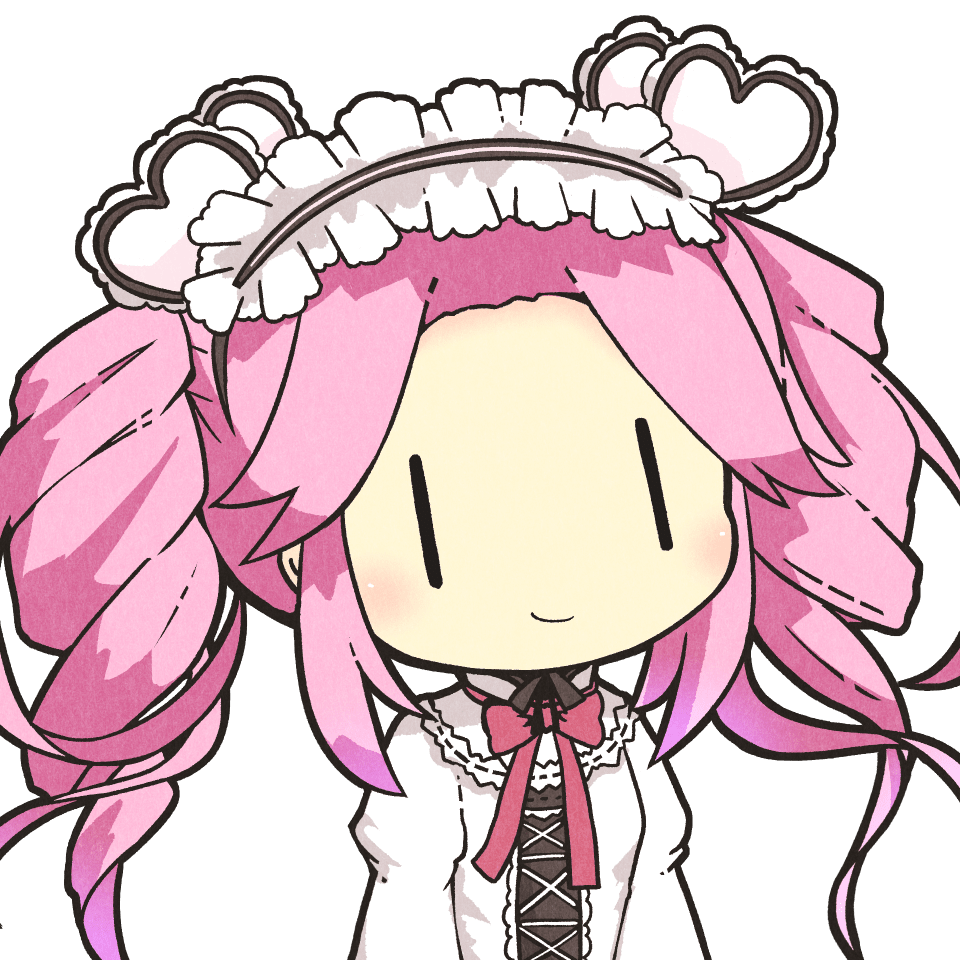



Discussion