マルチステージCIとGitOpsで実現するマイクロサービスのCI/CD戦略 - Kubernetes以外の環境への適用
■はじめに
先日公開した2つの記事では、マイクロサービス開発におけるCI/CD戦略と、Kubernetesを使わないGitOpsライクな運用について解説しました。
最初の記事では、Argo CDやFluxといったKubernetesネイティブなGitOpsツールを前提とした、CI/CDの責務分離モデルを提案しました。しかし、オンプレミスのVMや、AWS ECS/Lambdaといった非Kubernetes環境で、モダンなデプロイ戦略を模索している開発・運用チームも数多く存在します。
そこでこの記事では、元記事の戦略をKubernetes以外の環境へ適用する際の「差分」と、その差分を乗り越えるための具体的な実践方法に焦点を当てて解説します。この記事は、上記2つの記事の内容を結びつけるための、実践的なガイドです。
■アーキテクチャ
これから解説する4つの差分を乗り越え、非Kubernetes環境で一貫したCI/CDパイプラインを実現するためのアーキテクチャ全体像を以下の図に示します。
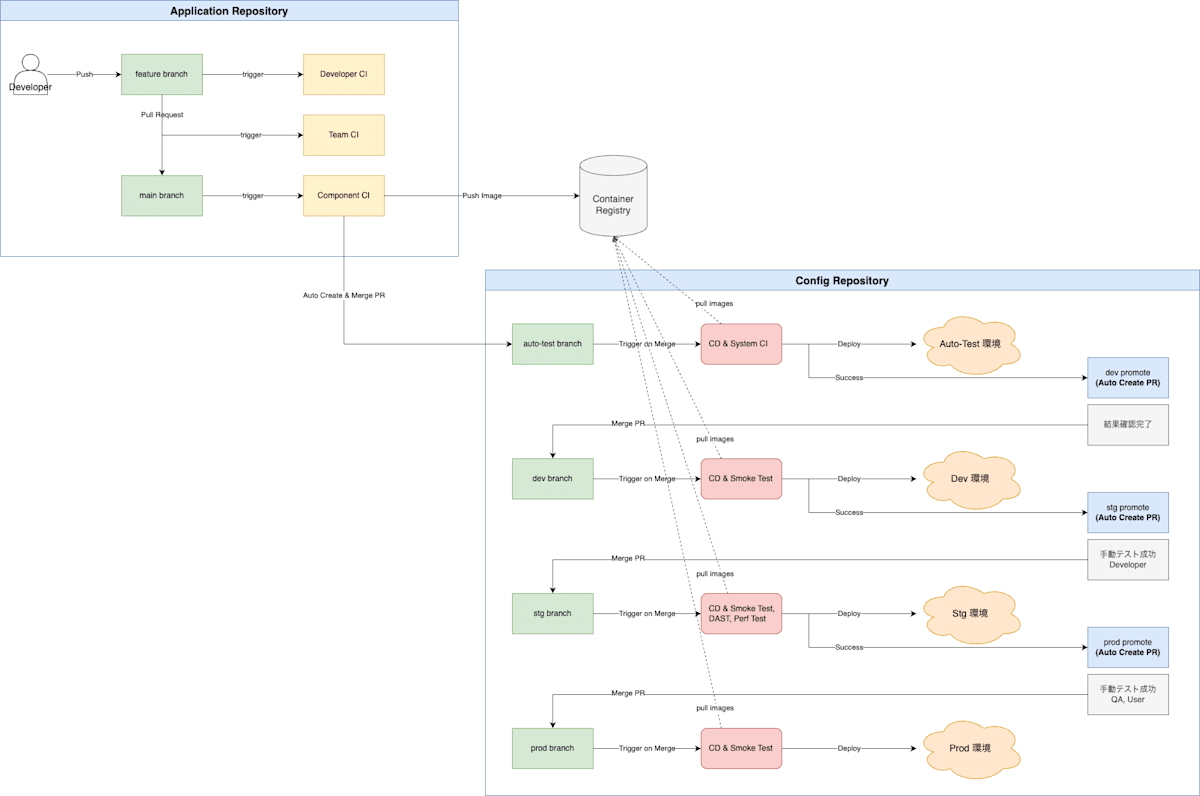
図1:非Kubernetes環境におけるマルチステージCI x Push型GitOpsのアーキテクチャ
このアーキテクチャの核心は、元記事と同様にCIとCDの責務をリポジトリレベルで完全に分離することにあります。
- アプリケーションリポジトリ (CI): 開発者がコードをプッシュする場所です。ここでのCIパイプラインは、高品質な「部品」(コンテナイメージやJARファイルなど)をビルドし、設定リポジトリへの変更要求(PR)を自動作成するまでが責務です。
-
設定リポジトリ (CD): 各環境(
dev,stg,prod)のあるべき状態を宣言的に管理します。ここでのCDパイプラインは、承認されたPRをトリガーに、Push型でターゲット環境へ変更を適用(デプロイ)します。
この図の流れを念頭に置くことで、以降に説明する各原則や差分への理解がより深まります。
■普遍的な原則:環境を問わず「変わらない」こと
まず重要なのは、元記事で提唱した戦略の中核部分は、実行環境がKubernetesかどうかに関わらず有効であるという点です。
- CI/CDの責務分離: アプリケーションリポジトリが「部品」を作り、設定リポジトリが「システム」を組み立てるという考え方。
- マルチステージCI: Developer CI, Team CI, Component CIを通じて、フィードバックを早期化し、高品質なアーティファクトを生成するプロセス。
- PRベースのプロモーション: ある環境での成功が、次の環境へのデプロイPRを自動作成する、安全で追跡可能なプロモーションフロー。
- Git Revertによるロールバック: 問題発生時に、設定リポジトリでコミットをrevertすることで、安全に以前の状態へ復元する原則。
これらの原則は、これから解説する差分を乗り越えるための土台となります。
■4つの重要な差分:非Kubernetes環境で「変わる」こと
元記事の戦略を非Kubernetes環境へ適用する際には、主に4つの重要な違いを理解し、対処する必要があります。
●差分1:状態管理モデルが「Pull型」から「Push型」へ
元記事で前提としたArgo CD/Fluxは、環境側からGitリポジトリを監視し、あるべき状態を プル(Pull) して自己の状態を同期させる「Pull型」です。
一方、非Kubernetes環境では、CI/CDパイプライン(例: GitHub Actions)がデプロイ対象の環境へ直接変更を プッシュ(Push) する「Push型」が、実装の容易さから現実的な選択肢となります。このモデルの違いが、後述するすべての差分の根源となります。
●差分2:「継続的リコンシリエーション」の不在と「ドリフト監査」の必要性
Pull型モデル最大の利点は、手動変更などで発生した「構成ドリフト」を自動で検知・修復する継続的リコンシリエーション機能です。Push型にはこの仕組みがありません。
【対策】 定期的な「ドリフト監査パイプライン」の実装
このギャップを埋めるため、デプロイパイプラインとは別に、Git上の「あるべき状態」と「実際の環境」を定期的に比較するドリフト監査パイプラインを構築することが不可欠です。例えば、Ansibleの--checkモードやTerraformのplanを定期実行したり、AWS CLIで設定値を取得してGit上の定義と比較したりすることで、ドリフトを検知し、GitOpsのワークフローに則った修正を促します。
サンプルコード:Ansibleによる定期的なドリフト監査 (GitHub Actions)
# .github/workflows/audit.yml
# 注意: このコードは概念を示すサンプルです。実際にはインベントリファイルやPlaybook、
# SSHキーなどのシークレットを適切に設定する必要があります。
name: Daily Infrastructure Audit
on:
schedule:
- cron: '0 2 * * *' # 毎日 AM2時に実行 (JST AM11時)
jobs:
ansible-check:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- name: Checkout config repository
uses: actions/checkout@v4
- name: Setup SSH Agent for Ansible
uses: webfactory/ssh-agent@v0.9.0
with:
ssh-private-key: ${{ secrets.PROD_SSH_PRIVATE_KEY }}
- name: Run Ansible in Check Mode
run: |
ansible-playbook \
-i inventory/production.ini \
--check \ # Check modeを有効化。実際の変更は加えない
playbooks/all.yml
# 実行結果に応じて、差分があればSlack通知やIssue起票を行う
●差分3:デプロイ後テストの実行主体と方法
元記事では、Argo CDのSync Hooksなどを使い、デプロイ完了をトリガーとしてテストJobを実行できました。Push型では、この責務をCDパイプライン自身が担う必要があります。
【対策】 CDパイプライン内でのステップ実行
GitHub ActionsなどのCDパイプライン内で、デプロイ用コマンドを実行するステップの直後に、Smoke TestやAPIテストを実行するステップを明示的に追加します。テストが失敗した場合はパイプライン全体を失敗させ、後続のプロモーションPR作成を中止するロジックが必須です。
サンプルコード:デプロイとテストを連携させるCDパイプライン (GitHub Actions)
# .github/workflows/cd.yml (抜粋)
jobs:
deploy-and-test:
if: github.ref == 'refs/heads/stg'
runs-on: ubuntu-latest
steps:
# (中略: Checkoutや認証設定)
- name: Deploy to Staging
id: deploy
run: |
echo "Deploying to Staging environment..."
# serverless deploy --stage stg などを実行
# 成功したデプロイ先のURLなどを出力
echo "endpoint=https://stg.api.example.com" >> $GITHUB_OUTPUT
- name: Run Smoke Test
id: test
run: |
echo "Running smoke tests on ${{ steps.deploy.outputs.endpoint }}"
# curlやテストスクリプトでエンドポイントを叩く
# テストが失敗した場合は exit 1 でジョブを失敗させる
exit 0
- name: Create PR to Production
if: success() # deployとtestの両ステップが成功した場合のみ実行
run: |
gh pr create \
--base prod \
--head stg \
--title "🚀 Promote changes from stg to prod" \
--body "All tests passed in the staging environment."
●差分4:デプロイ実装の多様化とクレデンシャル管理
Kubernetes環境ではマニフェストという共通言語がありましたが、非K8s環境ではデプロイツールが多様です(Ansible, Terraform, AWS CodeDeploy, Serverless Framework, 各社CLI、あるいは単純なシェルスクリプトなど)。
【対策】 ツール連携と安全な認証
-
ツール連携: CDパイプラインは、プロモーション先のブランチ名(
dev,stgなど)に応じて、AnsibleのインベントリファイルやServerless Frameworkのステージ名を動的に切り替えるロジックを持つ必要があります。 - クレデンシャル管理: Push型ではCI/CD基盤が本番環境のクレデンシャルを持つ必要があり、セキュリティリスクとなります。この対策として、クラウドプロバイダとのOIDC連携を活用し、永続的なキーではなく、実行ごとに発行される短期的なアクセストークンで認証することが強く推奨されます。OIDCが利用できない環境では、AWS Secrets ManagerやHashiCorp Vaultのような外部のシークレット管理ツールと連携し、実行時に動的に認証情報を取得する方法も有効です。
サンプルコード:OIDC連携とブランチに応じた動的なデプロイ (GitHub Actions)
# .github/workflows/cd-aws.yml
name: Deploy to AWS Lambda
on:
push:
branches:
- dev
- prod
jobs:
deploy:
runs-on: ubuntu-latest
permissions:
id-token: write # OIDC認証のために必要
contents: read
steps:
- name: Checkout code
uses: actions/checkout@v4
- name: Get branch name
id: get_branch
run: echo "branch=${GITHUB_REF#refs/heads/}" >> $GITHUB_OUTPUT
- name: Configure AWS credentials using OIDC
uses: aws-actions/configure-aws-credentials@v4
with:
role-to-assume: arn:aws:iam::123456789012:role/github-actions-deploy-role
aws-region: ap-northeast-1
- name: Deploy with Serverless Framework
uses: serverless/github-action@v3.3
with:
# ブランチ名(dev/prod)を Serverless Framework の stage として動的に渡す
args: deploy --stage ${{ steps.get_branch.outputs.branch }}
■まとめ
マルチステージCIとGitOpsの戦略は、特定のプラットフォームに縛られない強力な設計思想です。Kubernetes以外の環境へ適用する場合、以下の加味することで、その恩恵を最大限に享受することができます。
- ドリフト監査パイプラインで構成ドリフトを検知する仕組みを補い、
- CDパイプライン内でデプロイ後のテストを確実に実行し、
- OIDC連携などで安全な認証を実現する
これにより、皆さんのチームは、実行環境の制約を超えて、迅速で信頼性の高いソフトウェアデリバリーを実現できるはずです。
この記事が少しでも参考になった、あるいは改善点などがあれば、ぜひリアクションやコメント、SNSでのシェアをいただけると励みになります!
Discussion