フルスタックTypeScriptを採用すると何が嬉しい?
はじめに
プロダクト開発を行う際、フロントエンドはNext.jsで、バックエンドはRuby on RailsやLaravelで、といったアーキテクチャにすることが結構多いと思います
広く知られている構成で情報も多く、昔から使っていて慣れているエンジニアの方も多いです
その中で、フロントエンドもバックエンドも(なんならインフラも)TypeScriptで書くというアーキテクチャにも一定メリットがあり、技術スタックの候補に入れてもいいんじゃないかと筆者は考えています
今回は、そんなフルスタックTypeScriptのメリットやおすすめポイントについて紹介します
この記事を読んだ人が「今はTypeScriptだけでもいけそうだな」と少しでも思ってもらえると嬉しいです
3行まとめ
- プロダクトの開発言語が統一されていることでスイッチングコストが減り、エンジニアが今までよりもさらに開発分野を越境して動きやすくなる
- AI活用という文脈でフルスタックTypeScriptは明確に強みになる
- フルスタックTypeScriptにすることで、エンジニア採用や技術広報にも貢献できる
おすすめポイント
エンジニアが開発分野を越境して動きやすくなる
最近のプロダクト開発では、フルスタックエンジニアやプロダクトエンジニアのような開発分野を限定せず、プロダクト全体のエンジニアリングに素早く貢献できる職種、役割が注目され、価値が向上してきています
そういった中で、開発分野によって分業かつ異なる開発言語だと以下のような悩みが出てくると考えています
- 「機能改修をスピーディに行いたいけど、自分はRuby書けないからバックエンドエンジニアにAPIサーバーの修正を依頼しなきゃ」
- 「複雑な型定義やロジックで、TypeScriptだとこう書くけどRubyだとどう書くのが良いんだっけ?」
- 「TypeScriptとGoだと型定義で細かい違いがあるから、コードも修正してOpenAPIドキュメントも修正して・・・」
もちろんプロジェクトで採用されている複数の言語、ツールをそれぞれ習熟すれば良いといった考え方も出来るとは思いますが、それがTypeScriptだけで済むというメリットは一定大きいと考えています
また、型定義の共有やAPI仕様についてのやり取りにHono RPCなどを活用することで型安全性や開発速度の向上が見込めます
特にHonoについてはHono + Zod + OpenAPIで値や型の検証をスムーズに行えたり、OpenAPI Swaggerドキュメントを簡単に生成できたりといった部分に加えてWeb標準であること、豊富なプラグインなどメリットが大きいので、バックエンドフレームワークとして採用を検討する価値があると考えています
フルスタックTypeScriptとAI活用
プロダクト開発におけるAIコーディングツールの活用が進む中、フルスタックTypeScriptは明確な優位性を持ちます
AIツールは、型情報をガードレールとして活用することでより正確なコードを生成できるようになっています
また、型定義があることでAIモデルが無効な状態や型の不一致を推測しにくくなり、いわゆる「ハルシネーション(AIの誤った推測)」を軽減する効果も期待できます
フロントエンドとバックエンドをTypeScriptで統一することで、AI活用においてさらなる相乗効果が生まれます
モノレポ構成でフロントエンドとバックエンドで型情報の共有やHono RPCなどを活用すれば、フロントエンドからバックエンドまでエンドツーエンドの型安全性が実現でき、AIツールがフロントエンドとバックエンドの型の一貫性を理解した上で設計、実装を効率的に行えるようになります
AIがコードや開発言語をどれだけ学習しているか、という文脈においてもTypeScriptは優位性があると考えています
TypeScriptのリードアーキテクトであるAnders Hejlsbergは、GitHubのインタビューにおいて「あるプログラミング言語においてAIがコードを書く能力は、そのAIがその言語をどれだけ触れてきたか、学習しているかに比例する」と述べており[1]、そういった観点でもTypeScriptは豊富なトレーニングデータによってAIコード生成において優位性を持っています
エンジニア採用や技術広報への寄与
TypeScriptは今非常に注目され、コミュニティも盛り上がっている開発言語です
GitHubのOctoverse 2025では、TypeScriptが2025年8月の使用率でPythonとJavaScriptを上回り、GitHubで最も使用される言語になったと報じています[2]
世界的に見てもTypeScript最大級の国内カンファレンス「TSKaigi 2025」には2500名を超える参加者が集まり[3]、エコシステムを含むTypeScriptコミュニティ全体の盛り上がり、注目度が高いことが分かります
ZennのTypeScriptトピック記事は1万越え、人気のトピックとしても3位に位置しており、ネット上の情報も多いことがうかがえます
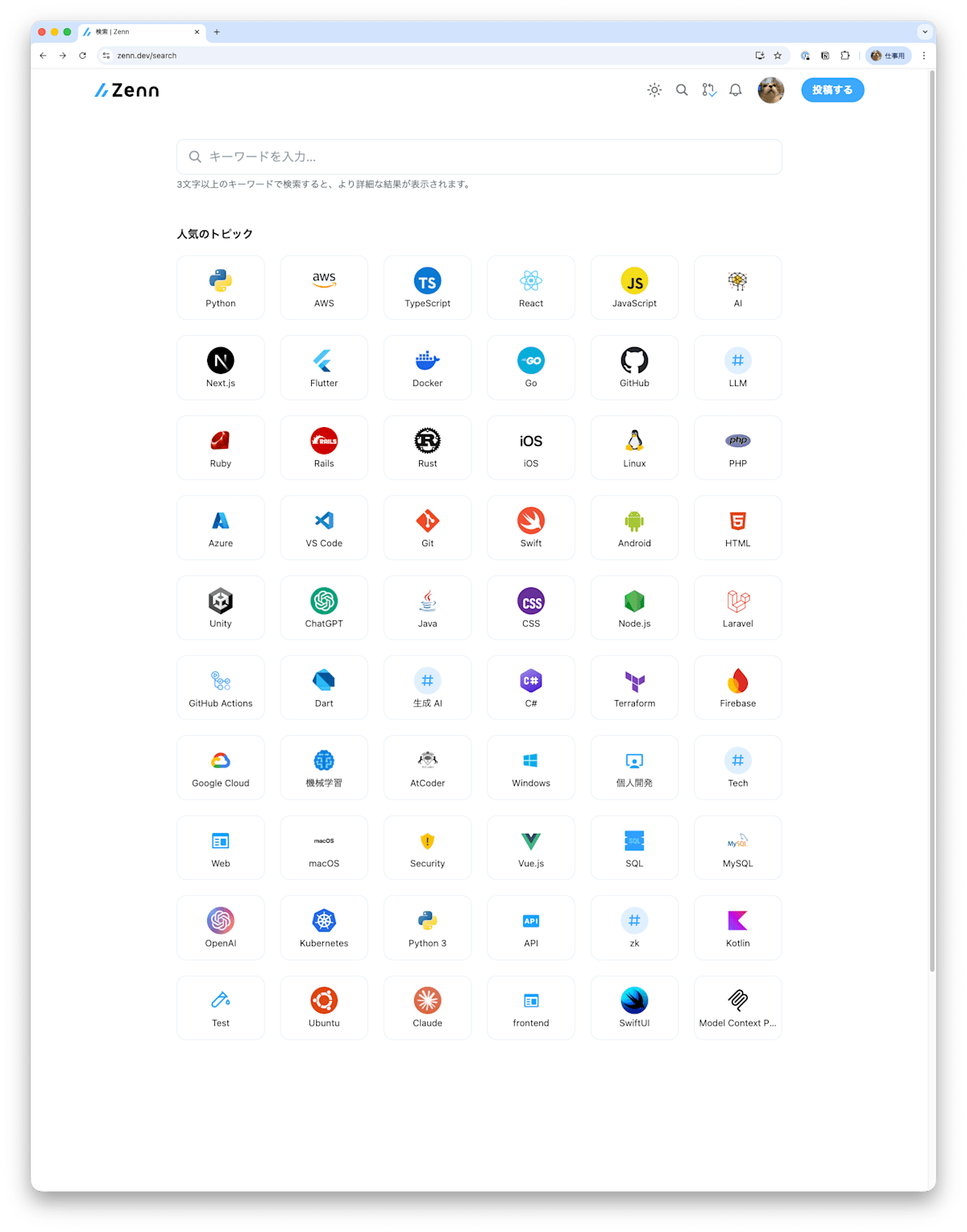
日本国内のエンジニア市場に限っても、TypeScriptを扱う求人やエンジニアの数は多いと考えられます
エンジニアの転職サービスを運営するFindyのサイトを見てみると、Node.js + TypeScriptで絞ったエンジニア求人は約3400件で、Node.js + TypeScript + フルスタックエンジニアで絞ったエンジニア求人は約900件となっており、バックエンドをNode.jsで構築し、開発言語としてTypeScriptを採用している企業も、その技術スタックでフルスタックエンジニアを求めている企業も多いという結果になっています
また、Findyが公開したIT/Webエンジニア転職動向調査 2025年3月号では「現在主に業務で使用している言語・技術を最大3つまでご選択ください」「今後習得または強化したい言語・技術を最大3つまでお答えください」という2つの設問においてTypeScriptが1位となっています[4]
同じようにFindyが公開しているIT/Webエンジニア企業動向調査レポート 2025年3月版では「AI活用を推進する上で、今後採用を強化したいポジションや職種を教えてください」という設問においてフルスタックエンジニアが最も多いという結果になっており[5]、フルスタックエンジニアも、TypeScriptという開発言語も、広く利用されていて求められていることがこちらの資料からも分かります
プロダクト側がフルスタックTypeScriptを採用していると、「TypeScriptを武器にプロダクトを横断して携わりたい」「1つの言語でプロダクト全体を見たい」と考えているエンジニアに対して強い訴求ポイントになります
また、コミュニティが盛り上がっていて広く使われている開発言語をフルスタックライクに活用することで様々な技術的知見が社内で溜まりやすくなり、その溜まった情報を社外に公開することで自社の技術的ブランディングにも繋がると考えています
まとめ
今回は、フルスタックTypeScriptにすることでどういったメリットがあるかについて、技術的な側面、企業が採用する上での側面で考えをまとめてみました
バックエンド開発における学習コストやエコシステムの成熟度など、いくつか懸念点やトレードオフはありますが、Webアプリケーション開発のアーキテクチャとして考えたとき、フルスタックTypeScriptを採用するメリットは一定あると考えています
最後まで読んでいただいてありがとうございました!
Discussion