TROCCOのSelf-Hosted RunnerをAmazon ECS(Fargate)で動かしてプライベートネット間の転送をしてみた
はじめに
2025/02現在、クラウドETL「TROCCO」では、任意の環境でデータ転送処理を完結できる、「Self-Hosted Runner」機能の開発が進められています。
この度、β版としてトライアルの受付が始まったので、実際に試してみました。
筆者について
筆者は、サービスの黎明期よりTROCCOの開発に従事、Self-Hosted Runnerの設計や実装の一部も行っている、いわゆる中の人です。
今回は、現時点での公開可能情報から、できる限り本機能のイメージを明確にしていただければと、執筆しています。
既存のTROCCOのアーキテクチャ
まず、既存のTROCCOのアーキテクチャについて軽く触れておきます。
TROCCOでは、データ転送ジョブが立ち上がると、弊社管理のAmazon EKS上でPodが立ち上がり、終了するとPodも破棄されます。
Pod内では、OSSのEmbulkで転送処理が行われつつ、その実行状況を管理するコードが動いています。
詳しくは「アーキテクチャConference2024」での拙スライドを参照ください。
課題
ここで問題となるのは、転送元/先のリソースがインターネットからアクセスできない場所にあるケースです。
SaaS系のコネクターは、トークンやID/Passwordによる認証があるとはいえ、インターネット上のどこからでもアクセス可能なことが多いです。
一方で、クラウドやオンプレミス上のデータベースやファイルストレージなどは、何かしらネットワーク面での制約があるはずです。
その場合、何らかの方法でTROCCOからアクセス可能となるように設定いただく必要があります。
例えば、踏み台サーバーを経由したり、AWSであればSSMやPrivateLinkを利用したり、といった具合です。
しかしながら、上記方法が使えない場合もありますし、踏み台経由にせよTROCCOのグローバルIPからのアクセスを明示的に許可いただく必要があります。
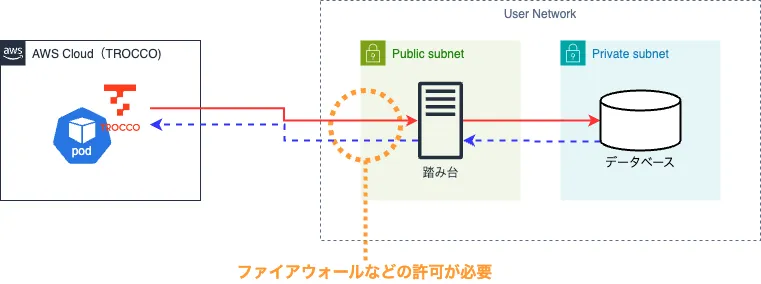
Self-Hosted Runnerのアーキテクチャ
前述の課題を解決するべく、Self-Hosted Runner機能ではコンテナイメージを配布して、データ転送処理部分をユーザーの任意の環境で行えるアーキテクチャを取っています。
一方で、設定の作成や管理は今まで通りTROCCOのサーバー上で行われる、ハイブリッドな形式です。
GitHub ActionsのSelf-Hosted Runnerを触ったことがある方は、それをイメージしていただけると分かりやすいはずです。
今回の題材
今回は、Amazon ECS(Fargate)上でコンテナを動かしてみます。
より価値を実感してもらうため、以下のような環境下での転送を題材にしてみます。
- 2つの異なるVPCのプライベートサブネット上でAmazon RDS(MySQL)が動いている
- 両ネットワークはVPC Peeringで繋がっているが、RDSへは外部からのアクセスができない
- 片方のVPC上でECSを動かすことを想定し、そこからのRDSへのアクセスを許可しておく
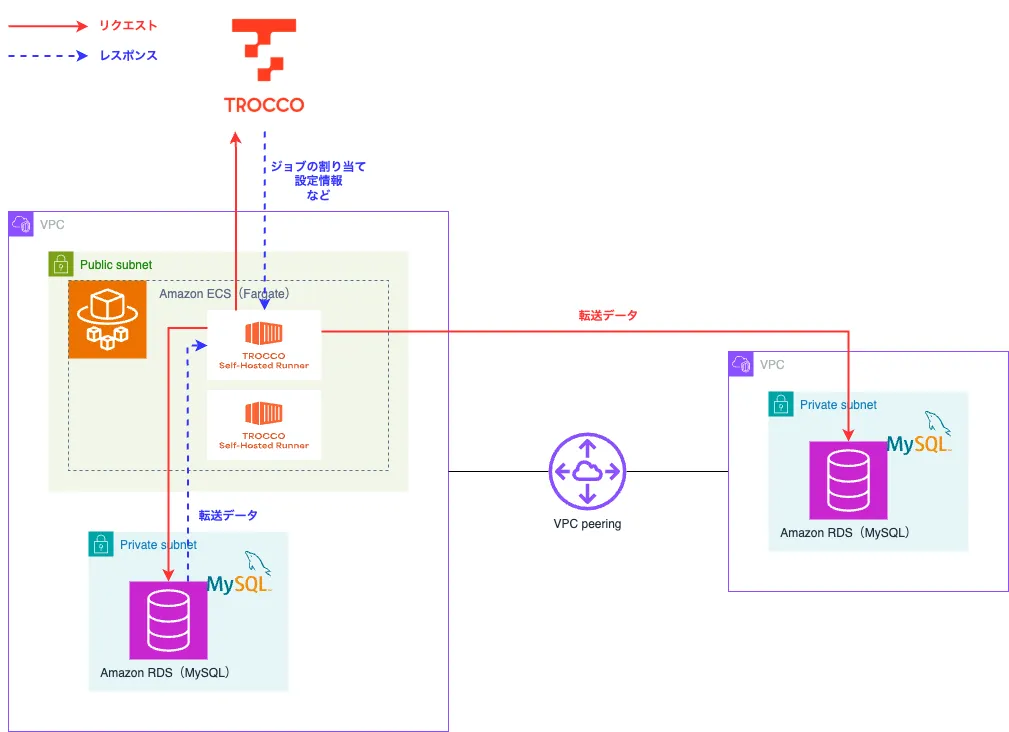
赤色の矢印(リクエスト)が、全てSelf-Hosted Runnerを起点に走っています。
データ転送処理が実行されるのはSelf-Hosted Runner上なので、転送元/先のリソースへアクセス可能な環境下で起動することで、ネットワーク的制約を乗り越えることができます。
上記の構成は機能に直接関係はしない一例ですが、再現性のためTerraformのHCLファイルを置いておきます。
(ECSに関連する部分は、後述で画面から作成しているため含まれていません。)
TROCCOとの通信
ハイブリッドな機能なので、Self-Hosted RunnerとTROCCOは随時を通信する必要があります。
例えば、以下が挙げられます。
- 死活監視のために、Runner側からTROCCO側へ、定期的にHeartbeatリクエストを行う
- ジョブが発火した際には、Heartbeatのレスポンスとしてその旨を受け取る
- ジョブ実行前に、Runnerg側からTROCCO側へ、必要な接続情報を取得しに行く
- ジョブ実行中に、Runnerg側からTROCCO側へ、実行ログを送信する
- ジョブ完了時に、Runner側からTROCCO側へ、ステータスを通知する
簡略図

その全てが、Sels-Hosted Runner起点となっていることが重要です。
例えば、AWSのSecurity Groupではステートフルな(返りのパケットは自動的に許可される)仕組みなので、アウトバウンドな設定が通れば通信できます。
また、一般的にアウトバウンドな設定は、厳しく制限されるインバウンドな設定に比べて、比較的緩めに設定されることが多いです。
このようなアーキテクチャを取ることで、既存のTROCCOでは難しかった要件を満たせるようになります。
Self-Hosted Runnerを動かす
それでは、実例に入っていきます。
クラスターの作成
Self-Hosted Runnerのオプションが有効な場合、TROCCOのサイドメニューに表示されます。

まずは、コンテナをまとめる論理的な概念である「クラスター」を作成します。

作成時にはトークンが発行されます。
セキュリティの都合上、一度しか表示されないため控えておいてください。
トークンは2つまで作成できるため、安全にローテーションが可能です。

例として表示されているDockerコマンド(docker pull, docker run)を実行することで簡単に立ち上げることができます。
docker runでは、環境変数として先ほどのトークンを指定してください。
Self-Hosted Runnerの1つの設計思想としてポータビリティがあります。
クラウドサービスや構成に寄らず、コンテナが実行できる環境であれば、1台から複数台まで互いに依存せずに立ち上げることができます。
極端な話、手元のPC上でも実行可能です。
とりあえず挙動を確認したい、といったアドホックな場合には有用でしょう。
ECSの設定
全体の構成はTerraformで作成しておきましたが、こちらは分かりやすさのため、マネージドコンソールから手動で準備していきます。
トークンの安全な管理
まず、トークンをセキュアにECSタスクへ設定すべく、System ManagerのParameter Storeに登録しておきます。
一手間かかりますが、こういうところはしっかりやっておきましょう。

TaskExecutionRoleの用意
ECSのTaskExecutionRoleに指定するためのIAM Roleを作成しておきます。
今回は、CloudWatch Logsへのロギング、Parameter Storeからの取得権限が必要です。
前者はマネージドポリシー(AmazonECSTaskExecutionRolePolicy)に含まれていますが、後者は自前で作成する必要があります。

{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowSSMParameterAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": ["ssm:GetParameter", "ssm:GetParameters"],
"Resource": [
"arn:aws:ssm:ap-northeast-1:<ACCOUNT_ID>:parameter/self_hosted_runner_token"
]
},
{
"Sid": "AllowKMSDecrypt",
"Effect": "Allow",
"Action": "kms:Decrypt",
"Resource": "arn:aws:kms:ap-northeast-1:<ACCOUNT_ID>:alias/aws/ssm"
}
]
}
ECSタスクにAmazonECSTaskExecutionRolePolicyと作成したポリシーを許可するIAM Roleを作成します。


ロググループの作成
CloudWatch Logsのロググループも事前に作成しておきます。
AmazonECSTaskExecutionRolePolicyには、ロググループを作成する権限がないためです。

セキュリティグループの作成
SecutiryGroupを作成しておきます。
アーキテクチャ上インバウンドなアクセスは発生しないので、アウトバウンドなルールだけ許可しておきます。

ECSクラスター
それでは、ECS自体の設定をしていきます。
今回は、Fargateを利用してECSクラスターを作成します。

ECSタスク定義
次に、ECSタスク定義を作成します。
Self-Hosted Runnerの最小推奨メモリは2GBです。
とりあえず、その値に設定しておきます。
タスク実行ロールでは先ほど作成したIAM Roleを指定します。

イメージのURIにはTROCCOの画面上に表示されていたものを指定してください。
インバウンドなリクエストを受け付けることはないため、ポートマッピングは指定不要です。
環境変数には、TROCCO_REGISTRATION_TOKENにValueFromでParametor StoreのARNを指定して埋め込みます。

ログ設定では、先ほど作成したCloudWatch Logsのロググループを指定します。

ECSサービス
最後に、ECSサービスを作成してデプロイします。
とりあえず、先ほど作成したタスク定義を1タスク起動する設定とします。

ネットワークは転送元側のパブリックサブネットで起動するようにしておき、先ほど作成したSecurity Groupを指定します。

タスクが起動し始めると、CloudWatch Logsでログが確認できます。
Joined cluster successfullyと出ていればひとまず成功です。

TROCCOの画面上からも確認できます。
まだジョブ待ち状態なのでIDLEステータスが表示されています。
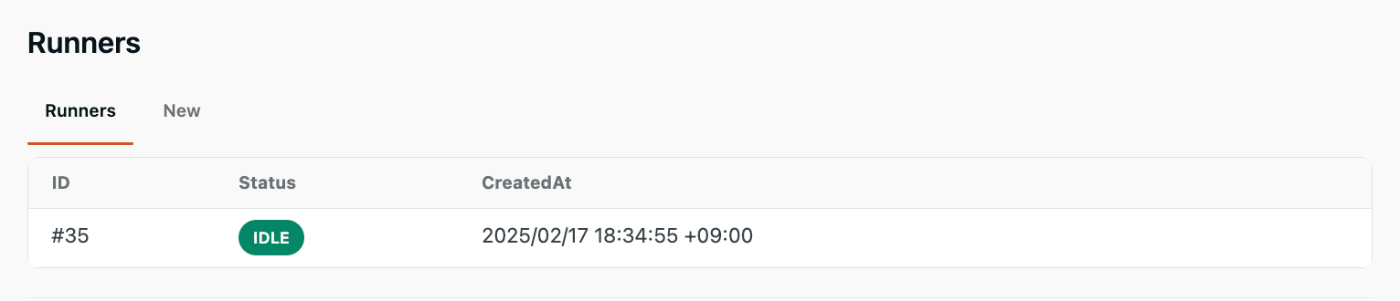
転送設定の作成
TROCCO側の設定に戻ります。
接続情報
まずは、それぞれのMySQLへの接続情報を作成します。
ホスト名が解決されるIPは、それぞれのプライベートサブネットのIPのため、従来のTROCCOであればもちろんアクセスできません。


転送設定
次に、転送設定を作成します。
Self-Hosted Runnerオプションが有効の場合、ジョブを動かすクラスターを選択可能です。
選択しないことも可能なので、ある設定は従来通りTROCCO上で動かし、ある設定は自前のコンテナ上で動かすこともできます。

その後は、設定を通常通り作成していきます。
Self-Hosted Runner機能の特徴として、設定を作成するフローは既存のTROCCOとシームレスという点があります。


プレビュー
STEP2へ進むと、従来通りプレビューが走ります。
ただしこちらは、Self-Hosted Runner上でEmbulkのpreviewコマンドが実行されています。

TROCCOの仕様上、スキーマ情報を決定するために必ずこのフローが必要になります。
しかしながら、セキュリティ都合上、実プレビューデータをTROCCOへ送ることを許可できないケースもあります。
この場合は、コンテナ起動時に環境変数TROCCO_NO_SEND_PREVIEW=trueを渡すことにより、必要不可欠なカラム情報のみが送られるようにできます。

ジョブ実行
それでは、データ転送ジョブを実行してみます。
CloudWatch Logsを見ると実行ログが流れ始めました。

TROCCOの画面上でも、RunnerのステータスがACTIVEになっています。

無事成功しました。

転送先のMySQLを覗いてみます。
実際にデータが入っていることも確認できました。

CPUを増やしてみる
ECSタスク定義でvCPU数を増やしてデプロイしてみます。
TROCCOの裏側で利用しているEmbulkは、CPU数に比例して並列度が上がります。
コネクタの組み合わせや諸条件次第なので、一概に処理時間が比例的に短くなるわけではないですが、試してみましょう。
今回は、1vCPUから8vCPUに上げてみます。

新しいタスク定義でサービスを更新します。

新しいタスクが立ち上がりました。

同一の転送設定を実行してみると以下になりました。

以下の先ほどの結果と比較すると、20秒弱早くなったことが確認できました。

このように、ユーザー側で柔軟にリソースを調整できることも、Self-Hosted Runnerの価値の1つです。
並列度を上げてみる
ECSサービスでタスク数を4に設定してデプロイしてみます。

その後、転送ジョブを同時に4件起動してみます。
それぞれのRunnerがACTIVEステータスになっており、並列でジョブが実行されていることが確認できます。

おわりに
今回は、TROCCO Self-Hosted Runnerが解決する課題、技術仕様、実際の構築例まで、広くご紹介させていただきました。
トライアルも受け付けておりますので、ご関心をお持ちの方はサービスページからお問合せください。
Discussion