私がAIスタートアップに勤めて、数ヶ月で辞めた話 ~ベンチャーのメリット・デメリット
私がAIスタートアップに勤めて、数ヶ月で辞めた話 ~ベンチャーのメリット・デメリット
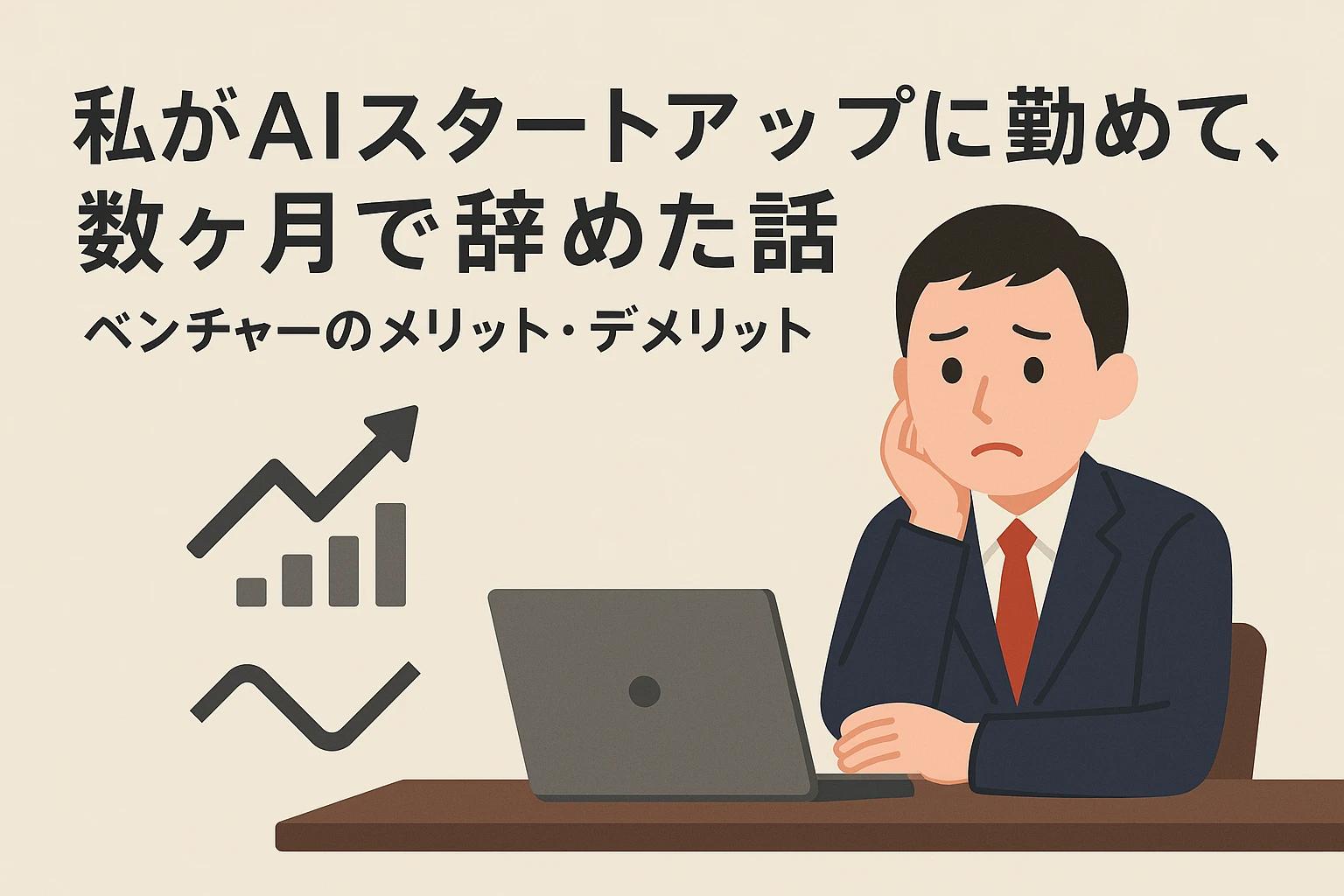
はじめに
AIをはじめとするスタートアップやベンチャー企業は、近年ますます注目を集めています。
「新しい技術に触れられる」「裁量が大きい」「スピード感がある」──そんな期待を抱いて転職する人も少なくありません。
私もその一人で、かつて、エンジニアとしてスキルアップを狙い、創業間もないAIスタートアップに入社しました。その会社は、AIを用いたBtoB向けサービスを開発する小規模企業で、当時のエンジニアは私と直接の上司の2人だけ。あとは、経営者と営業担当が数名いるだけの体制でした。
結論から言えば、半年もしないうちに退職することになりました。ただし、この短い期間での経験は「スタートアップで働くとはどういうことか」を理解する上で、非常に大きな学びになりました。本稿では、その実体験を整理し、スタートアップのメリット・デメリットを客観的に振り返りたいと思います。
スタートアップを選んだ理由
私はもともとはマーケティング会社でWebエンジニアとして働いていましたが、担当範囲はごく一部の機能開発に限られていました。もっと幅広い領域を経験し、自分のアイデアを直接実装に反映させたい──そう考えて転職活動を始めました。
面接では「フルスタック的に色々触ってほしい」「勤務形態も柔軟」と説明され、裁量の大きさに魅力を感じました。大企業の枠から抜け出し、スピード感ある環境で挑戦できると思ったのです。
入社直後の現実
前述したように、エンジニアが少ないこともあり、本来であれば複数人で分担するはずのタスクを、私一人で回す必要がありました。
-
教育制度は存在しない
入社初日、まず驚いたのは 事業説明もオンボーディングも一切なかった ことです。
席に案内された直後に「このアプリにバグがあるから直して」と依頼されました。が、サービスの全体像すら知らない状態。ドキュメントは存在せず、仕様の理解はソースコードを読み解くしかありませんでした。 -
Git運用も未整備
リポジトリを確認すると、ブランチ戦略や命名規則は存在せず、Issue管理もなし。唯一の情報源は「上司の頭の中」で、こちらが「どのブランチを使うのか」「いつまでに仕上げればよいか」を尋ねても「その辺はベンチャーだから自分で考えて」と返されるだけでした。 -
タスクは丸投げ
ある日、アプリのバグ修正を依頼されたときのことです。「修正したコードをどこに反映すればいいか」「デプロイ前にどんなテストが必要か」と確認すると、「そんなの決まってないから適当にやって」で会話終了。
ルールがないこと自体は想定していましたが、最低限の共有もなく丸投げ される状況には流石に戸惑いを隠せずにはいられませんでした。
メリットに感じた点
一方で、この環境だからこそ得られた学びもありました。
-
成長速度の速さ
誰も作業を分担してくれないので、フロントエンドからバックエンド、インフラ、デプロイまで一人で担当せざるを得ませんでした。
結果として、開発から運用までの一連の流れを短い期間で体験できました。前職ではコードを書くだけだったので、この経験はたいへん貴重なものでした。 -
周辺技術を自ら習得
Dockerの設定、クラウド上でのサーバー構築、ログ監視、セキュリティ設定など、日々新しい問題に直面し、調べながら解決する必要がありました。効率的ではありませんが、幅広い技術に触れるきっかけになりました。 -
裁量の大きさ
仕様が曖昧なため、自分で決めて進めるしかない。逆に言えば、自分の判断で設計や実装を行える自由度がありました。 小さな改善でも即座に反映できる環境は、一般の会社ではなかなか得がたい経験だと思います。
顧客先でのインフラ復旧を経験ゼロのまま任されたこともありました。今では良い思い出ですが、当時はリスクの高さに心臓バクバクになりながら対応したのを覚えています。
デメリットに感じた点
-
人材不足と属人化
上司もエンジニアではありましたが、実情としては、経営や営業も兼ねており、コードを書くことはほぼありませんでした。結果として、上司の知識やノウハウが委譲できず、また、私も自前でコードを読み解きながら、実装を進めるしかなかったため、社内でノウハウが共有できない、属人化が進みました。 -
方針の不安定さ
昨日言われたタスクが翌日には覆る。追加で別の仕様変更が入り、完成間際のコードを作り直すこともしばしば。ドキュメントが存在しないため、変更の理由や背景も不明確 でした。結果、コードはスパゲッティ化し、作業効率は下がる一方でした。 -
労働環境
スタートアップの忙しさも相まって、残業は日常茶飯事でした。私は朝10時からの勤務ではありましたが、基本的にオフィスを去るのは深夜22時以降となるのが常態化していました。
また、休日や深夜に突然呼び出されることもあり、プライベートと仕事の境界が結構曖昧になっていたと思います。 -
コミュニケーション不足
最も辛かったのは相談・説明体制の欠如です。
例えば、重要な仕様変更がSlackの短いやり取りだけで共有され、正式な記録や背景説明が残されない ことがありました。
その結果、私が実装したコードが「実は不要になっていた」と判明することもしばしば。
情報の抜け漏れが積み重なり、無駄な作業や手戻りが増える状況に悩まされました。
退職を決断した理由
最終的に退職を決めたのは、相談やフィードバックの機会が少なく、学習環境として限界を感じたこと でした。任される裁量は大きかったものの、フォローがなく成果だけを求められる状況は、私にとって長く続けるのは難しいと判断しました。
また、組織としての体制やルール、相談できる仕組みが整っていなかったため、自分の成長に必要な要素が欠けている と感じました。十分に学びを得られた一方で、このままでは成長が頭打ちになるだろうと考え、退職を選ぶことにしました。
結果的に退職を選びましたが、この経験を通じて 「自分が成長するために必要な環境条件」 を明確にできたのは大きな収穫でしたし、幅広い技術に触れられたことに関しては、今でも力になっています。(私も、後輩のエンジニアには、「一度フルスタックで実装する経験を積んだ方が良い」 と言うほどになりました。)
学んだこと・得たもの
この経験を通じて、以下の気づきを得ました。
-
技術だけでなく環境が重要
どれほど技術的な挑戦があっても、相談やフィードバックの機会がなければ成長は頭打ちになる。 -
裁量は諸刃の剣
自分で決められる自由は大きな学習機会となるが、同時に責任も全て負うことになる。支えがない状態では消耗しやすい。 -
働く上で重視すべき要素
給与やスキルセット以上に、「相談できる関係性」や「基本的なルール整備」が欠かせない。
この気づきはその後のキャリア選びに活き、次の職場を決める際には「教育体制の有無」「相談できる文化」「ルール整備」を必ず確認するようになりました。
改善できたかもしれない点(自己反省)
もちろん、自分にも改善の余地はありました。
-
入社前に教育体制の有無を確認せず、勝手に期待していた。
-
丸投げタスクをそのままこなすだけでなく、最低限のルールやフローを自ら提案すべきだった。
-
上司の曖昧な指示に対して、背景や意図を深掘りする質問が不足していた。
こうした主体的な対応があれば、もう少し円滑に働けた可能性もあったのかな、と今では思います。
まとめ
スタートアップは短期間で多様な経験を積める一方、リソース不足や環境未整備というリスクが常に存在します。私の数ヶ月は厳しいものでしたが、フルスタックでの実務経験や「環境を見極める視点」を得られた点で非常に有意義ではありました。
これからスタートアップを目指す人には、メリットとデメリットを冷静に見極め、「自分がどんな環境で成長できるのか」を事前に考えて選択すること を強く勧めます。
Discussion