ゼロから圏論をHaskellで実装するサンプルの一例
概要
圏論を勉強していると,人それぞれの記法があることが分かる.
恐ろしいことに,一人につき一つ,何なら1冊につき一つレベルである(半ギレ).
さらに,Haskellでの実装しようにも,Haskell自体が型と関数の圏と呼ばれており,圏の中で圏を作るってどうなの?(全ギレ)
そこで,無茶苦茶抽象的な実装ではなく,もっと具体的な例を作ってみる.
Haskellを試すときはコンパイルではなく,ghciを起動し続けながらチェックすべし!
実行例
f x = x + 1 -- を書いたファイルtest.hsを作ったら
>ghci
-- で起動して,
-- 関数fを試したり
ghci> f 1
2
-- :tで関数fの型を確認したり,
ghci> :t f
f :: Num a => a -> a
-- :iで詳しい情報を見たり,
ghci> :i f
f :: Num a => a -> a -- Defined at test.hs:1:1
-- 変更を加えたら:rでリロードしたりする.
ghci> :r
Ok, one module loaded.
Haskellの読み方の基本
- haskellのすべては,型と式である.(変数も式扱い.ややこし)
なぜ型と式だけなのか?
それはラムダ計算がチューリング完全だからである
あらゆる計算・アルゴリズムを行うのが個別のチューリングマシンで,
それら個別のチューリングマシンを全て1基で再現できるのが万能チューリングマシンで,
ラムダ計算は万能チューリングマシンと等価であるチャーチ=チューリングのテーゼがあって,
証明するには万能チューリングマシンを再現できることが証明された2タグシステムと同じだと証明されたウルフラムの2記号3状態チューリングマシンを再現できることを証明すればよい.マインクラフトやマリオメーカーなども,そうやって別の万能チューリングマシンを再現して証明してるらしい.
(wikiより,多少改変)
- 型は右結合
A->B->C = A->(B->C)で大文字始まり - 式は左結合
f x y z = ((f x) y) zで小文字始まり - 型を決めて,定義を決めるまでが,関数自作の1セット.
数式で書くと
と定義する.
である.
このように関数に2を入れて計算することを,Haskellでは関数適用という.fを2に適用して3になる.
コードで書くと
f :: Int -> Int -- 型の定義と
f x = x + 1 -- 式の定義
result = f 2 -- 関数適用
resultは3になる.
各部分の用語を書くと
-- はコメントアウトです.
-- 関数 :: 型シグネチャ
関数 :: 型 -> 型
関数 値引数 = 式
となる.
ホントは
用語いろいろ(量がグロいので序盤は見ないほうがいいかも)
-- data, classなどは構文なのでそのままにする
-- 対象:集合:型
data C = A | X | Y deriving (Show, Eq)
data 型名 = 値コンストラクタA | 値コンストラクタX | ...
data 圏C = 対象A | 対象X | ... -- として扱う
-- deriving (Show, Eq)は,型Cを表示Showと比較Eqが出来る型にするという意味.ShowやEqは型クラス
-- 関手の定義
class Functor f where
fmap :: (a -> b) -> (f a -> f b)
-- 関手fなら射(a -> b)も射(f a -> f b)に写せるよな?の意味
class 型クラス 型 where
型クラスにした型に付与する機能の定義
instance Functor F_cls where
fmap f (F x) = F (f x) -- F(f)(F(x))
instance 型クラス 型クラスを付与する型 where
fmap 射の写し方のルール設定
以上,用語をまとめると,以下のようになる.ここで一度,用語の多さにキレておくとよい.
| 用語 | 実装例 | 一言 |
|---|---|---|
| 型 | C, F_cls C | 圏として扱う.必ず大文字 |
| 値コンストラクタ | A, X, F A, G X | 対象として扱う.必ず大文字 |
| 式・関数 | f, g, h | 射として扱う |
| 型シグネチャ | C, F_cls C | 射のどっからどこへの詳細情報 |
| 引数 | a, b, x, y | 必ず小文字 |
| 型クラス | Show, Eq, Functor, Applicative | 型に機能を追加する |
| 型コンストラクタ | F_cls a, G_cls a | 型引数aを取っている"型" |
| インスタンス | F_cls, G_cls | 型に型クラスの機能を付与したもの |
他にも,具体型:F_cls Intのように型コンストラクタに型を具体的に入れたやつとか,
ファンクター値,アプリカティブ値:それぞれのインスタンスの具体的な値F Yとか,
めちゃくちゃあるが,今は無視していい.
圏
- 圏論の全ては射で説明できるらしいが,そうは言われても分らんので,圏論=対象と射の学問ととらえる.
- 圏は,射の合成条件:結合律と恒等射により,うまい具合に関係性を保って議論できる.(コヒーレンス則?)
記法(tex)と定義wiki
圏
- 対象の類
A,X,Y \in Obj(\mathscr{C}) = \{A,X,Y\} - 射の類
f,g,h,h' \in Mor(\mathscr{C}) = \{f,g,h,h',id_A, id_X, id_Y, id_Z\} - 結合律を満たす射の合成
h \circ f - 単位律を満たす恒等射
id_A, id_X, id_Y
からなる. - 結合律は順番どれでもOK条件で,
h' \circ h \circ f = (h' \circ h) \circ f = h' \circ (h \circ f) - 単位律はどっちから来ても射はそのままです条件で,
id_A \circ f = f = f \circ id_X, id_X \circ h = h
以上が圏の定義である.
また,可換とは,ルートの異なる(始域と終域が同じだが射が異なる)射の交換が可能なことを指す.
(類は集合のあやふやバージョン.集合の集合(族)とかも含んでいる)
手書き

真ん中のぐるぐるが可換を表す.ぐるぐるするというより置き換え可能というイメージのほうが良い.
Haskell
-- 対象:集合:型
data C = A | X | Y | Z deriving (Show, Eq)
-- 射:関数
f :: C -> C
f A = X
g :: C -> C
g A = Y
h :: C -> C
h X = Y
h' :: C -> C
h' Y = Z
-- 恒等射
idA :: C -> C
idA a = a
idX :: C -> C
idX x = x
idY :: C -> C
idY y = y
idZ :: C -> C
idZ z = z
-- 以下,恒等射にはデフォルトで搭載されているidを用いる.
-- 射の合成
--- 以下,===で同じという意味を表すことにする
-- テスト(h.f) A === 結果Y
-- 結合律
-- (h'.h.f) A === ((h'.h).f) A === (h'.(h.f)) A === Z
-- 可換かどうか
result1 = (h.f) A
result2 = g A
kakan = (result1 == result2) -- Trueなので可換 h.f=g
関手
ここからHaskellの難所.
記法ルール(tex)と定義
関手
関手
と書き,以下の条件を満たす.
-
X,Y\in Obj{\mathscr{C}} F(X),F(Y)\in Obj{\mathscr{D}} -
f:X\to Y F(f):F(X)\to F(Y) - 結合律は,
h\circ f F(h\circ f) = F(h)\circ F(f) - 単位律は,
id_A F(id_A)=id_{F(A)}
手書き
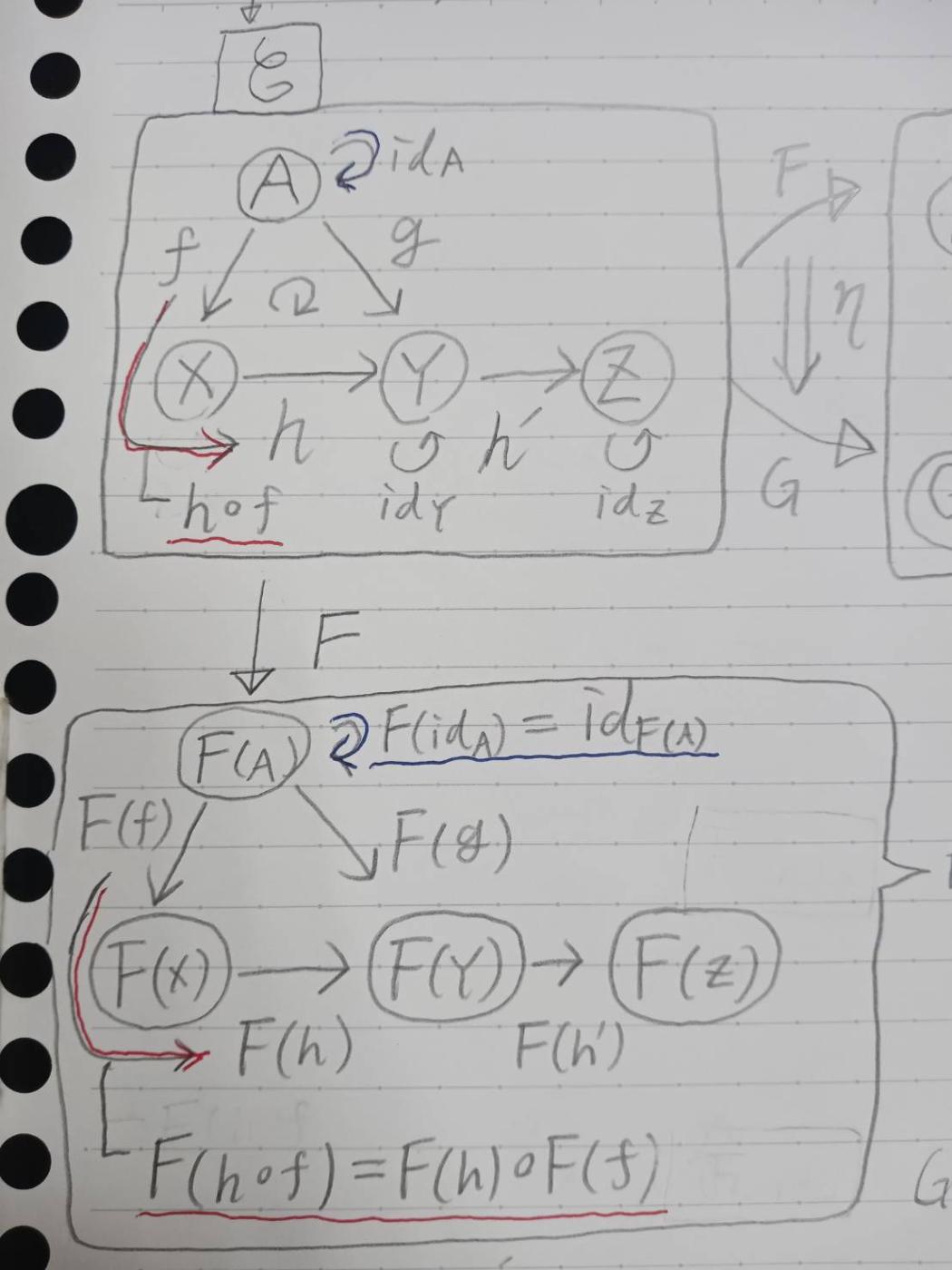
Haskell
-- FunctorとApplicativeは中身の確認のため自作するので隠しておく
import Prelude hiding (Functor(..), Applicative(..))
{-
この辺に圏で書いたコード
-}
-- 関手の定義 --
class Functor f where
fmap :: (a -> b) -> (f a -> f b)
-- 関手fなら射(a -> b)も射(f a -> f b)に写せるよな?
class (Functor f) => Applicative f where
-- aを受け取って,アプリカティブ値(f a)を返す.つまり対象写す
pure :: a -> f a
-- fmap強化版つまり射写す
(<*>) :: f (a -> b) -> (f a -> f b)
-- 対象(型)を作る
data F_cls a = F a deriving (Show)
-- 中身を関手化
instance Functor F_cls where
fmap f (F x) = F (f x) -- F(f)(F(x))
instance Applicative F_cls where
pure x = F x
F f <*> F x = fmap f (F(x)) -- = F (f x) = F(f)(F(x))
-- 関手の条件 --
-- 射を正しく写しているか?:F(f) <*> F(A) === F(X)
(<.>) :: F_cls (b -> c) -> F_cls (a -> b) -> F_cls (a -> c)
F h <.> F f = F(h.f)
-- 結合律:F(h.f) <*> F(A) === F(h) <.> F(f) <*> F(A) === (F Y)
idFA :: F_cls C -> F_cls C
idFA a = a
-- 恒等射:F(idA) <*> F(A) === idFA(F(A)) === F(A)
自然変換
こいつが厄介.
「自然な~」という初心者からすると超不自然な単語の元凶
私は圏論から学び始めたので,関手の上位互換だと勝手に誤解していたが,射は写さない.繰り返す.関手と異なり射は写さない
記法ルール(tex)と定義
自然変換
左下ルート=右上ルートで可換である.
また,複数の射の束であり,2次元的に広がることから,以下のようにも書かれる
手書き
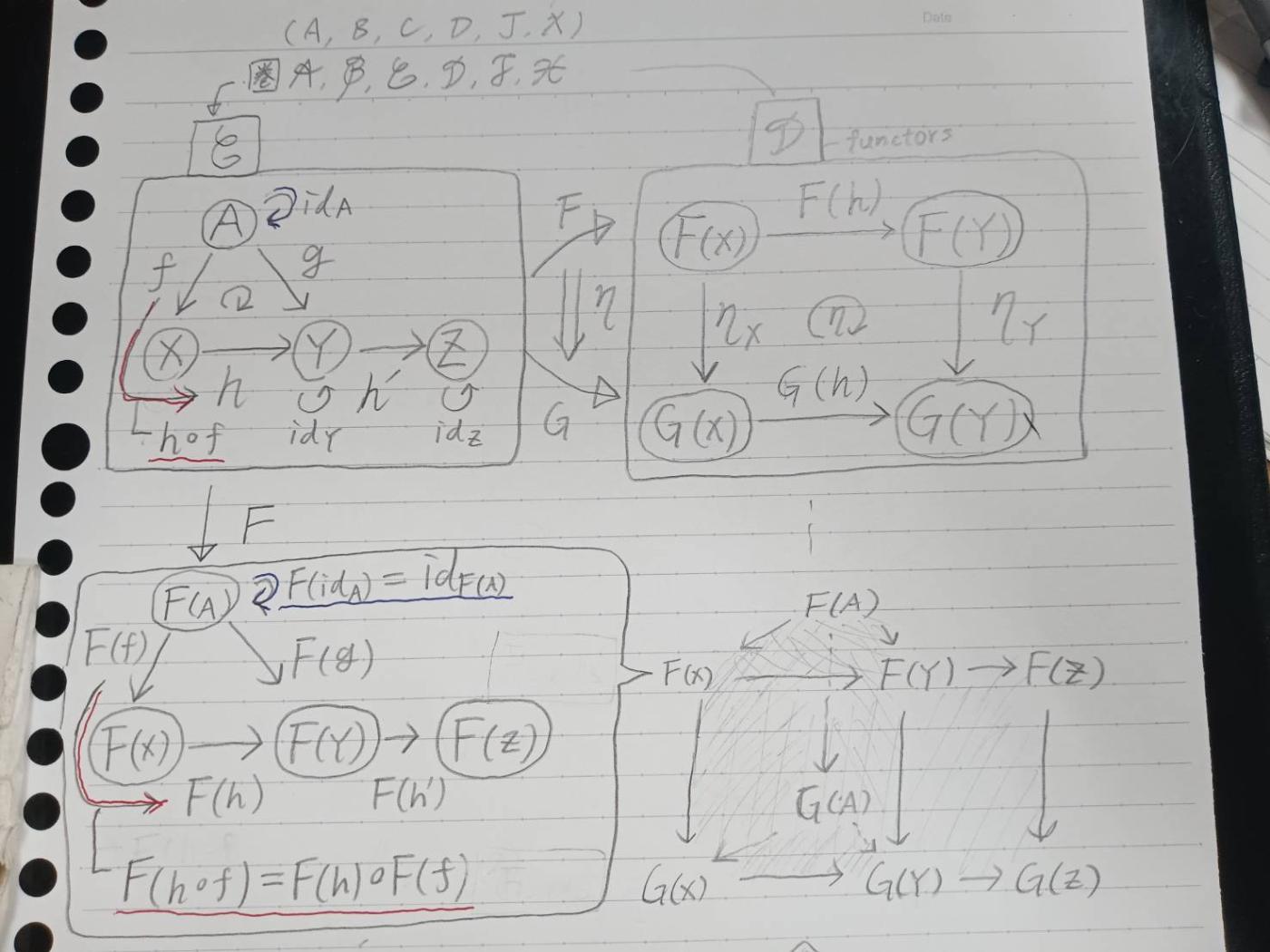
全て書き出すと立方体のようになる.
対象が点で射が辺,自然変換が下に延び3次元になる.
Haskell
-- ここから上は圏と関手のコード
-- 関手をもう一個用意:G
data G_cls a = G a deriving (Show)
instance Functor G_cls where
fmap f (G x) = G (f x) -- F(f)(F(x))
instance Applicative G_cls where
pure x = G x
G f <*> G x = fmap f (G x) -- = F (f x) = F(f)(F(x))
-- 自然変換nを定義
n_A :: F_cls C -> G_cls C
n_A(F(A)) = G A
n_X :: F_cls C -> G_cls C
n_X(F(X)) = G X
n_Y :: F_cls C -> G_cls C
n_Y(F(Y)) = G Y
n_Z :: F_cls C -> G_cls C
n_Z(F(Z)) = G Z
n = [n_A, n_X, n_Y, n_Z] -- 自然変換は上記のセット
-- 可換条件
-- G(h) <*> (n_X(F X)) === n_Y(F(h)<*>F(X)) === G Y
自然変換を適用するやり方が,数式に寄せれず少し悔しく思っている.
米田の補題
調整中.分らなすぎる.
リバースエンジニアリングできるっぽい
よ談
米田埋め込みを表す数学記号として,日本語平仮名の"よ"が使われてたことがあったらしい.
余米田の補題が存在
なんだかとってもうれしいね.
全コードまとめ
-- 20240516_0:42_完全に理解した
-- 20240624_圏論なんもわからん
-- 型と関数の圏Hask
-- FunctorとApplicativeは中身の確認のため自作するので隠しておく
import Prelude hiding (Functor(..), Applicative(..))
-- 対象:集合:型
data C = A | X | Y | Z deriving (Show, Eq)
-- 射:関数
f :: C -> C
f A = X
g :: C -> C
g A = Y
h :: C -> C
h X = Y
h' :: C -> C
h' Y = Z
-- 恒等射
idA :: C -> C
idA a = a
idX :: C -> C
idX x = x
idY :: C -> C
idY y = y
idZ :: C -> C
idZ z = z
-- 以下,恒等射にはデフォルトで搭載されているidを用いる.
-- 射の合成
--- 以下,===で同じという意味を表すことにする
-- テスト(h.f) A === 結果Y
-- 結合律
-- (h'.h.f) A === ((h'.h).f) A === (h'.(h.f)) A === Z
-- 可換かどうか
result1 = (h.f) A
result2 = g A
kakan = (result1 == result2) -- Trueなので可換 h.f=g
-- 関手の定義 --
class Functor f where
fmap :: (a -> b) -> (f a -> f b)
-- 関手fなら射(a -> b)も射(f a -> f b)に写せるよな?
class (Functor f) => Applicative f where
-- aを受け取って,アプリカティブ値(f a)を返す.つまり対象写す
pure :: a -> f a
-- fmap強化版つまり射写す
(<*>) :: f (a -> b) -> (f a -> f b)
-- 対象(型)を作る
data F_cls a = F a deriving (Show)
-- 中身を関手化
instance Functor F_cls where
fmap f (F x) = F (f x) -- F(f)(F(x))
instance Applicative F_cls where
pure x = F x
F f <*> F x = fmap f (F(x)) -- = F (f x) = F(f)(F(x))
-- 関手の条件 --
-- 射を正しく写しているか?:F(f) <*> F(A) === F(X)
(<.>) :: F_cls (b -> c) -> F_cls (a -> b) -> F_cls (a -> c)
F h <.> F f = F(h.f)
-- 結合律:F(h.f) <*> F(A) === F(h) <.> F(f) <*> F(A) === (F Y)
idFA :: F_cls C -> F_cls C
idFA a = a
-- 恒等射:F(idA) <*> F(A) === idFA(F(A)) === F(A)
-- 関手をもう一個用意:G
data G_cls a = G a deriving (Show)
instance Functor G_cls where
fmap f (G x) = G (f x) -- F(f)(F(x))
instance Applicative G_cls where
pure x = G x
G f <*> G x = fmap f (G x) -- = F (f x) = F(f)(F(x))
-- 自然変換n
n_A :: F_cls C -> G_cls C
n_A(F(A)) = G A
n_X :: F_cls C -> G_cls C
n_X(F(X)) = G X
n_Y :: F_cls C -> G_cls C
n_Y(F(Y)) = G Y
n_Z :: F_cls C -> G_cls C
n_Z(F(Z)) = G Z
n = [n_A, n_X, n_Y, n_Z] -- 自然変換は上記のセット
-- 可換条件確認
-- G(h) <*> (n_X(F X)) === n_Y(F(h)<*>F(X)) === G Y
Discussion